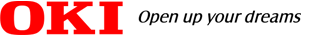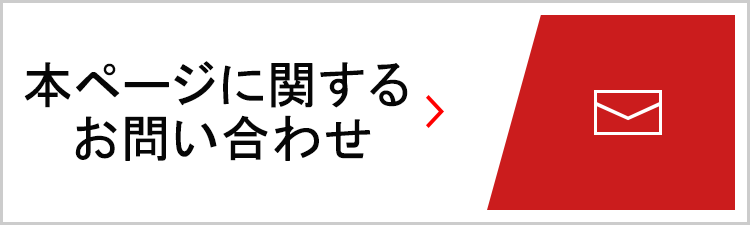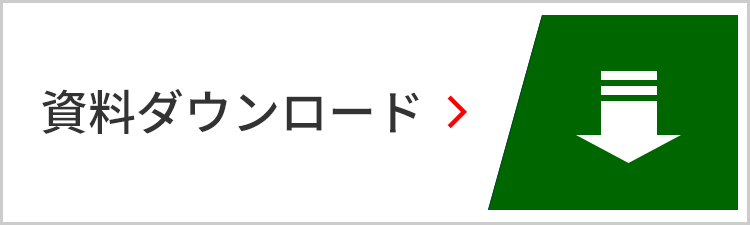- Home
- 受託試験サービス
- 化学分析(RoHS・REACH・環境)
- 環境分析
- 騒音対策調査
化学分析(RoHS・REACH・環境)
騒音対策調査: 騒音の計量証明事業所として東京都計量証明事業登録を行っており、騒音規正法に則り、騒音測定調査を実施
騒音対策調査
騒音規正法第5条には、「指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。」と定められており、法で定まられている騒音が発生する特定施設を設置している工場等(特定工場)は、敷地境界において工場から発生する全ての騒音を対象に、規制値を遵守しなければなりません。規制値は「騒音レベル(dB)」で表します。OKIエンジニアリングは、騒音の計量証明事業所として東京都計量証明事業登録を行っており、騒音規正法に則り、騒音測定調査サービスを実施しています。騒音測定はJIS Z 8731:1999「環境騒音の表示・測定方法」に準拠して行いますが、規制値は、都道府県毎の条例により、用途地域と時間帯で規制値が異なるため、各自治体に確認が必要です。 さらに、工場の稼働状況により測定しなければならない時間帯が異なりますが、24時間操業の工場の場合、朝、昼間、夕、夜間の各時間帯に測定を行います。また、騒音規制以外にも、以下のような騒音測定を実施いたします。
- 作業環境騒音測定:労働安全衛生規則「騒音障害防止のためのガイドライン」
- 防音工事助成のための測定:地方自治体(東京都など)
- ISO14000に関わる環境測定:騒音が「著しい環境側面」である場合
東京都計量証明事業登録
東京都計量検定所へ音圧レベルの証明事業登録を行っています。
騒音規制法の特定施設(騒音規制法第2条、施行令第1条、別表第1)
| 騒音規制法の特定施設(騒音規制法第2条、施行令第1条、別表第1) | |
|---|---|
| 1 | 金属加工機械
イ) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) ロ) 製管機械 ハ) ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) 二) 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ホ) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) ヘ) せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) ト) 鍛造機 チ) ワイヤーフォーミングマシン リ) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) ヌ) タンブラー ル) 切断機(と石を用いるものに限る。) |
| 2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
| 3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
| 4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
| 5 | 建設用資材製造機械 イ) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る。) ロ) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) |
| 6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
| 7 | 木材加工機械 イ) ドラムバッカー ロ) チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) ハ) 砕木機 二) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) ホ) 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ) ヘ) かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) |
| 8 | 抄紙機 |
| 9 | 印刷機(原動機を用いるものに限る。) |
| 10 | 合成樹脂用射出成型機 |
| 11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
騒音規制法の特定工場等に係る規制基準
騒音測定法第4条
昭和44年2月20日都告示第157号
| 区域の区分 |
時間の区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当てはめ地域 | 朝6時~8時 | 昼間8時~19時 | 夕19時~23時 | 夜間23時~6時 | |
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 ※1 AA地域 清瀬市松山3丁目 竹丘1丁目及び3丁目の一部 前号に接する地先及び水面 |
40dB | 45dB | 40dB | 40dB |
| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 ※2 第1特別地域 無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く。) |
40dB | 50dB | 45dB | 45dB |
| 第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) ※2 第2特別地域 前号に接する地先及び水面 |
55dB | 606dB | ←20時 55dB |
50dB |
| 第4種区域 | 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) ※2 第3特別地域 前号に接する地先及び水面 |
60dB | 70dB | 60dB | 55dB |
| ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域、第2特別地域を除く)における規制基準は、当該値から5dBを減じた値を適用する。 | |||||
備考
- デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。以下騒音に関して同じ。
- 騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
- 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法により、騒音の大きさの値は、次に定めるところによる。
- 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする。
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90%レンジの上端の数値とする。
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。
- ※1:AA地域の指定
平成12年3月31日都告示第420号(騒音に係る環境基準の地域類型の指定) - ※2:特別地域
2段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周囲30m以内の範囲
学校環境衛生の基準による騒音環境及び騒音レベル
学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図るため、学校保健法 学校環境衛生の基準(平成4年 文部省体育局長裁定)により定められています。
| 項目 |
内容 | |
|---|---|---|
| 検査項目 | 騒音環境及び騒音レベル | |
| 検査回数 | 毎学年2回定期に行う | |
| 検査事項 | (1)騒音環境 | 普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べる。 |
| (2)騒音レベル | 環境調査によって騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。等価騒音レベルの測定は、積分・平均機能を備える普通騒音計(JIS C 1502:1990)又はそれ以上の精度の測定器を用い、A特性で5分間、等価騒音レベル(LAeq)を測定する。なお、従来の普通騒音計を用いる場合にあっては、普通騒音から等価騒音を換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する。 | |
| 測定方法 | JIS Z 8731:1999「環境騒音の表示・測定方法」 | |
| 判定基準 | 教室は、校内・校外の騒音の影響を受けない環境が望ましく、教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB(デシベル)以下であることが望ましい。 | |
| 事後措置 | (1)窓を開けたときの等価騒音レベルが55dB(デシベル)以上となる場合 窓を閉じる等、適切な方法によって音を遮る措置を講じるようにする。 |
|
| (2)判定基準を超える場合 騒音の発生を少なくするか、普通教室等、長時間使用する教室は、騒音の影響が少ない教室を選ぶ等の適切な措置を講じるようにする。 |
||
- 騒音対策調査に関するお問い合わせ先
- WEBからのお問い合わせ:お問い合わせフォームはこちら
電話:03-5920-2356